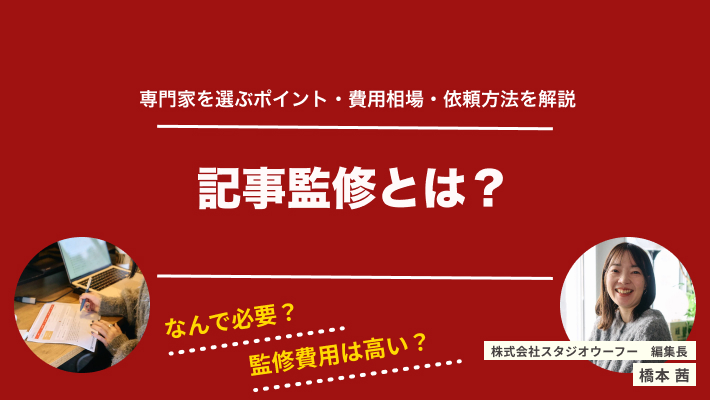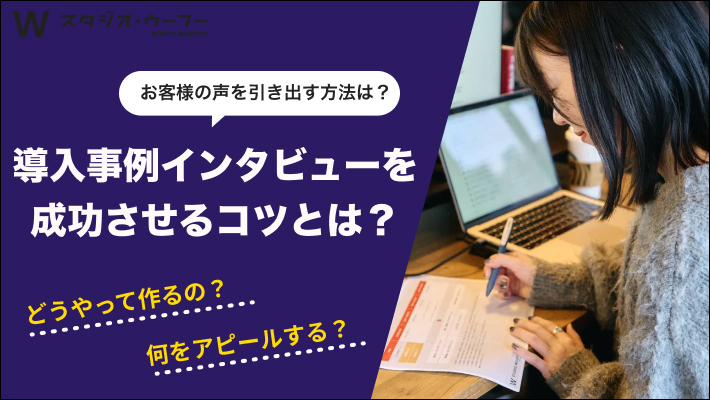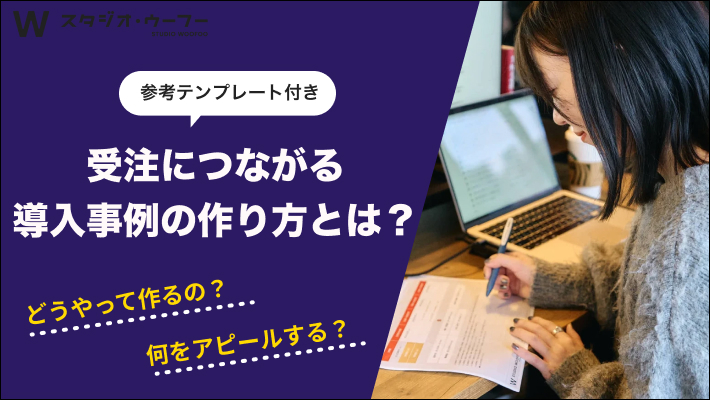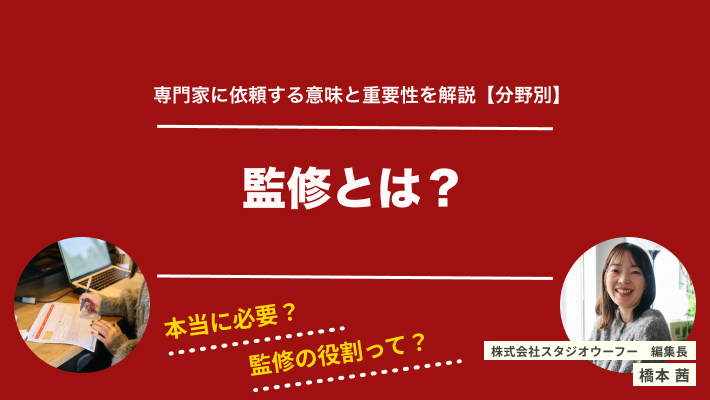
監修とは?専門家に依頼する意味と重要性を解説【分野別】

監修
プロデューサー
谷古宇浩司
20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修
編集企画チーム/リーダー
橋本茜
1992年、大分生まれ。大学在学中に編集の仕事に憧れ、ブランディング会社で経験を積む。その後、現場のディレクションを学ぶために上京し、女性マーケティングを主軸とした編集プロダクションに勤務。アパレルを中心にカタログ制作やファッション誌の企画、撮影や誌面のディレクションを経験した。紙媒体だけでなく、Web業界での経験や知見も深めるため、2021年に株式会社アンドストーリー/株式会社スタジオ・ウーフーに入社。これまでの経験を活かし、編集ディレクターとして多種多様なコンテンツ制作に従事しつつ、チームマネジメントも手がける。
監修とは?本当に意味あるの?

「監修」とは、書籍やWeb記事、商品、映像などの内容を専門家がチェック・監督し、内容の正確性や妥当性を保証することを指します。
監修者に選ばれるのは、その分野の専門知識を持ち、第三者としての視点から内容を確認・修正・補足できる人です。具体的には、医師や弁護士、大学教授などが含まれます。
専門家の視点が入ることで、情報の正確性や信頼性が高まるだけでなく、コンテンツの品質が引き上げられるのです。
監修は「監督・編集・プロデュース」とは違う?

監修と似たニュアンスで使われる言葉に、監督・編集・プロデュースがありますが、いずれも意味が異なります。ここではそれぞれの意味や役割について、比較してお伝えします。
監修は「監督・編集・プロデュース」とは違う?
監督の役割|作品全体を統括する
監督は、製作する作品の全体を統括する仕事であり、情報の正確性を検証する監修とは目的が異なります。監督は、作品制作の企画から完成までの全工程を統括し、指揮を取ったりチェックを行ったりします。
映像や舞台の現場では、シナリオをどう映像化するか、どのようなトーンで見せるかをなどを決め、撮影現場では演者やスタッフに指示を出すのです。また、撮影後の編集段階でも、カット割りや音楽の使い方、テンポ感などを最終的に判断します。
編集の役割|情報を整理し、伝わりやすくする
監修が「正確さを保証する」作業であるのに対し、編集は「情報をどう伝え、どう感じてもらうか」を決め、作品を作り上げていきます。
編集は、原稿や映像素材などの情報を整理し、受け手にとってわかりやすい構成に整えるだけでなく、作品やコンテンツ全体の方向性を設計するのが仕事です。
例えば、記事コンテンツの作成の場合は、テーマ設定や取材方針の段階から関わり、リサーチ・構成案の策定・タイトル設計・原稿修正・デザイン監修・最終校正までを一貫して担います。
プロデュースの役割|企画や資金を動かす
監修が「内容の正しさ」に責任を持つのに対し、プロデュースは「企画を形にする工程」に責任を持つのが仕事です。
プロデュースは、企画立案からチーム編成、スケジュールや予算の管理までを行い、プロジェクト全体を成功に導くための調整と意思決定を担います。
どの専門家を起用するか、どのターゲット層に届けるか、どの媒体で展開するかなど、全体像をデザインしていきます。
【分野別】監修の役割とは?
監修の重要性や目的は、対象となる分野によって少しずつ異なります。ここでは代表的な4分野を見ていきましょう。
料理|有名シェフ・管理栄養士など
料理・食に関する監修は、「おいしさ」や「健康・安全性」を保証するうえで欠かせません。コンビニや飲食店などで、有名なシェフや栄養管理士が監修したメニューを見かけることも多くなりました。
有名シェフ
有名シェフは、飲食・食品・外食産業において、味覚と調理技術の専門家として監修を担っています。「○○シェフ監修」という名前を冠した商品は近年、コンビニやスーパーなどで数多く見られます。
例えば、イオンの「おうちで楽しむプロのひと品」というシリーズでは飯塚隆太シェフや田村亮介シェフが監修したメニューを発表し、SNSでは「高級料理店の味を手軽に楽しめる」と話題となりました。
シェフ監修商品は、販促時にシェフの名前と制作過程をSNSやYouTubeで紹介することで「開発ストーリー」がユーザーの共感を呼び、拡散効果を得やすくなります。
管理栄養士
管理栄養士は、食品・健康・医療・教育など多岐にわたる分野で監修を担っています。管理栄養士が監修に加わることで、商品の栄養バランスや成分表示の妥当性が保証されます。
また、近年では、健康経営や機能性表示食品の開発など、企業の社会的信頼を高める取り組みにおいて貢献しているのです。
例えば、健康宅配弁当サービス「nosh(ナッシュ)」は、管理栄養士およびシェフが監修した冷凍弁当を販売しています。豊富なメニューが好評で、2025年には累計販売食数が1億2,380万食にのぼったと報告されています。
デザイン|建築家・デザイナーなど
建築やデザインの分野では、監修者の存在が「美しさ」だけでなく、「安全性・機能性・ブランドの一貫性」などを保証する要素になります。
とくに、複数の企業・職人・クリエイターが関わるプロジェクトでは、監修者が全体の方向性を示すことで、作品としての統一感と社会的信頼性を確保できます。
建築家
建築家の監修は、建物や街区全体の意図・品質・安全性を保ちながら、美しい景観を維持することに貢献します。
2017年に東京に開業したホテル「ONE@Tokyo」は、建築家である隈研吾氏が外観やインテリアのデザインを監修しています。街の雰囲気にあった高級感のあるデザインと、世界的に有名な隈研吾氏が監修という点で評判になりました。
デザイナー
デザイナーが監修することで、製品・ブランド・空間などの「見た目」や「使い勝手」を科学的かつ感覚的に設計し、商品の魅力やブランド印象を高められます。
仕様や素材の選定からレイアウト・色彩・ユーザー体験に至るまで、ブランドとして一貫した「世界観と品質」が保証される例もあるのです。
例えば、生活雑貨ブランドMUJI(良品計画)は、グラフィックデザイナー原研哉氏をアートディレクターとして起用し、2002年以降ブランドイメージと統一されたデザインを展開しています。
娯楽コンテンツ(書籍や映画)|歴史学者・民俗学者など
映画・ドラマ・小説・アニメなどの創作物では、誤った設定や描写は信頼を損ねるうえ、続きを楽しむユーザーが減ったり炎上したりするリスクがあります。
史実や他の文化などに基づいた作品の場合は専門家の監修が必要不可欠です。
歴史学者
映像や文学の世界では、「史実に基づく正確な描写」と「世界観の説得力」を保証するのが歴史学者監修の役割です。史実と齟齬があると、ユーザーが不信感を抱くことになるため、その正確性を担保する必要があります。
映像作品や演劇などで使われる道具や内容がその時代のものに合っているかどうかを監修することを、時代考証とも呼びます。
例えば、戦国時代にまつわる著書の多い健康科学大学特任教授である平山優さんは、複数のNHK大河ドラマの時代考証に携わっています。
民俗学者
民俗学者は、地域文化・風習・信仰・言語など、人々の生活に根ざした文化的要素の監修を担っています。監修が入ることで、作品や商品における文化描写の正確性や、創作物の文化的信頼性と説得力を高められます。
とくに、伝承・祭礼・民話などをモチーフとするコンテンツでは、民俗学者の知見がリアリティを支え、誤解や文化的摩擦を防ぐ役割を果たします。
2021年に公開された「チロンヌプカムイ イオマンテ」では、千葉大学名誉教授である中川裕氏が言語や内容について監修に携わりました。
生活に欠かせない分野|医師・弁護士など
医療・法律・金融など、人の生活や命に関わる情報領域では、間違った情報の記載が深刻な被害につながるリスクがあります。
Googleは検索品質評価ガイドラインの中で、この分野のコンテンツにおいて特にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視すると明言しています。
医師
医師は、医療・美容・健康など幅広い分野の監修に携わっており、商品・サービスの「医学的な正確性の担保」と「消費者の安心感の獲得」に貢献しています。
医師の臨床知見が反映されることで、より効果的な使い方が提案できるうえ、効果に関する情報の信頼性も高まり、ユーザーは安心して利用できます。
例えば、花王の敏感肌向けスキンケアブランド「キュレル(Curel)」では、皮膚科医の協力のもと研究開発されることがあります。
科学的根拠に裏打ちされた製品開発がブランドの信頼を支え、2024年の敏感肌用化粧品市場で売り上げ1位を記録しています。
弁護士
弁護士は、契約・労務・知的財産など、法的リスクを伴う領域で監修を担い、企業やメディアにおけるコンプライアンスの維持と情報の正確性向上に寄与しています。
専門家が関与することで、法制度に関わる複雑な内容でも整合性が保たれ、読者や利用者に誤解のない情報を届けることが可能です。
代表例として、電子契約サービス「クラウドサイン」があります。同サービスは、現職の弁護士が企画・設計段階から携わっており、法的根拠に基づいた仕組みとして構築されています。
契約業務にまつわる疑問やリスクに対しても、弁護士が監修するプロダクトであることが法的信頼性の裏づけとなり、多くの企業利用を後押ししています。
コンテンツマーケティングにおける監修の効果

企業のオウンドメディアの運営やSNS投稿などにおいても、監修はE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の各要素を高める重要な手段です。
E-E-A-Tを高めることで、検索エンジンからの評価だけでなく、ユーザーからの信頼やブランドの社会的信用も向上できます。
コンテンツマーケティングにおける監修の効果
専門性(Expertise)を担保できる
専門家に監修してもらうことで、コンテンツの根拠や背景に「科学的・技術的な裏付け」が生まれます。
近年のSEO事例では、監修者の実名・所属・資格を明示した記事が上位表示されやすくなっています。
専門家監修を入れることでその企業がその分野に精通しているという印象を与えられるのです。
権威性(Authoritativeness)をアピールできる
監修者の肩書きや経歴が明示されると、発信全体に社会的な裏付けが生まれます。
例えば「国立大学教授監修」「現役医師監修」「一級建築士監修」などの表記があると、その権威性により、匿名の記事よりもはるかに信頼されやすくなるのです。
加えて、監修者がメディア出演や論文発表の実績を持っている場合、その人物の知名度と企業ブランドが相乗効果を生みます。
信頼性(Trustworthness)を獲得できる
監修の最大の価値は、読者や顧客に「この情報は安心して信じられる」と思ってもらうことにあります。
とくに企業発信では、誤った情報や誇張された表現を使うことによってブランドイメージが損なわれるリスクがあるため、注意が必要なのです。
監修を導入することで、発信前に事実確認や根拠チェックを行い、炎上や批判を未然に防げます。
経験(Experience)を組み込める
監修者が現場で得たリアルな知見や失敗談、研究成果を加えることで、コンテンツの深みが増します。
単なるデータや理論にとどまらず、「実際のケーススタディ」「現場での改善例」「患者や顧客とのエピソード」などを補足できるのは、経験ある監修者ならではの強みです。
例えば、歯科医師監修のマウスピース矯正記事で「患者200人を診てわかった傾向」を語ることで、机上論ではなく実践的な説得力が生まれます。
監修の成功事例と失敗事例
専門家にコンテンツやサービスを監修してもらったことで成功した事例と、監修をしっかりとしなかったことで失敗した事例を紹介していきます。
監修の成功事例と失敗事例
成功事例|「医師が作った化粧品」として支持を獲得。業界を牽引する存在に
皮膚の専門家が開発した化粧品として知られるドクターシーラボ(Dr.Ci:Labo)は、「医師が作った」という明確な監修体制をブランドの中核に据え、国内外で高い信頼を獲得しています。
2000年代以降はテレビ通販や百貨店、ECサイトなどへ販路を拡大し、いまではアジアを中心に海外展開も進め、累計販売数6,000万個超を突破するヒット商品へと成長しました。
医師監修ブランドであることを活かし、広告・パッケージ・Webサイトなどすべてで「科学的根拠」「皮膚臨床データ」などを明示することで、専門性と安心感の両立を実現しています。
成功事例|「低糖質 大豆めん」がヒット。YouTubeやSNSで流行
iFood(アイフード)の「低糖質 大豆めん」は、糖尿病専門医・青木厚先生の監修により、超低糖質・高タンパクで安心して食べられる主食代替食として話題になりました。
発売直後から医療機関の糖尿病教室や学会で紹介され、医師や栄養士がSNSやYouTubeでその味や栄養設計を評価しました。
これらの専門家発信をきっかけに一般の方たちの間でも口コミが広がり、発売1か月で定期購入者が想定の3倍に達するなど、医療・ヘルスケア分野発のヒット商品となったのです。
失敗事例|医療メディア「WELQ」の失墜。全記事が公開停止に
2016年11月、DeNAが運営していた医療情報サイト「WELQ(ウェルク)」は、専門家監修のない不正確な医療記事を大量に公開していたことが問題視され、全記事を非公開としました。
健康や生命に関わる誤情報を拡散していると批判が相次ぎ、薬機法違反の可能性も指摘されました。
DeNAは「医学的知見を有する専門家による監修がなされていない記事が含まれていた」と事実を認め、すべての記事の再監修を実施すると発表したのです。
企業が医療や健康情報を扱う際、専門家監修の欠如がブランド失墜と事業停止の危険性に直結することを示す事例となりました。
失敗事例|東京オリンピックエンブレム問題。監修・確認体制の欠如で使用中止に
2015年、東京2020オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムが、ベルギーの劇場ロゴと酷似しているとして盗用疑惑が持ち上がり、採用から約1か月で使用中止となりました。
第三者による類似デザインの調査や、法的リスクを確認する専門家レビューが十分に行われていなかったことが原因とされています。
その後、組織委員会は新たに外部委員や弁理士を含む審査・監修体制を整備し、再公募を実施しました。
監修者の探し方
知り合いに監修できそうな専門家がいない場合は、以下のような方法で探すのが有効です。
監修者の探し方
公式HPやSNSで直接連絡をする
監修を依頼したい専門家を見つけたら、大学や病院、士業事務所などの公式HP経由で問い合わせます。SNS(InstagramやXなど)で専門家の名前を検索し、アカウントがあればDMを送るのも有効です。
依頼時は、失礼のないよう丁寧な文面を心がけ、監修の目的や報酬、掲載内容を端的に伝えるようにしましょう。
監修サービスを利用する
最近は、専門家と繋げてくれる監修マッチングサービスも増えてきました。
監修を引き受けてくれる可能性の高い専門家が登録しているため、スムーズなやり取りが可能で、急いで監修して欲しい場合にも使いやすいです。
幅広いジャンルの中から、分野別に適した専門家を紹介してもらえます。
監修者プロフィールの重要性とは?
監修をしてもらったコンテンツには、監修者の氏名・所属・資格・実績・顔写真・略歴などがわかるプロフィールを必ず明記しましょう。
せっかく監修をしてもらっても、プロフィールで監修者の専門性を伝えられなければ読者やユーザーの信頼を得られません。
プロフィールの記載は、その監修者が実在することの証明であり、情報の正確性と責任の所在を明らかするのです。
ぴったりな監修者が見つからない方へ
ジャンルによっては、コンテンツの内容にぴったりの監修者がなかなか見つからない場合もあります。探すのに時間がかかると、コンテンツ制作のスケジュールに支障をきたしかねません。
スタジオウーフーは、監修可能な各分野の専門家のご紹介が可能です。また親会社アンドストーリーと共にあらゆるコンテンツ制作を行っています。コンテンツの内容から一緒に考案できますので、ぜひ一度ご相談ください。