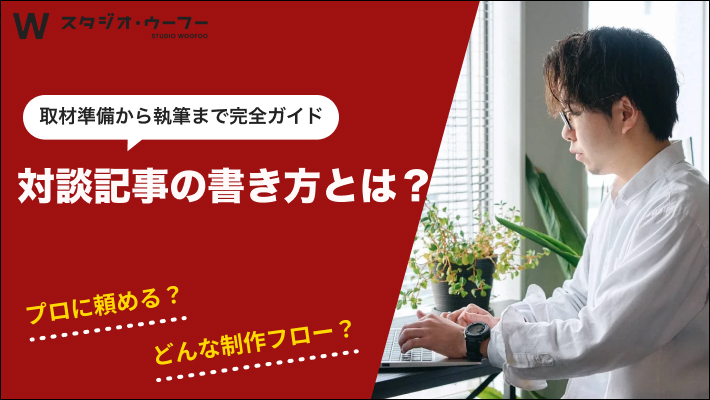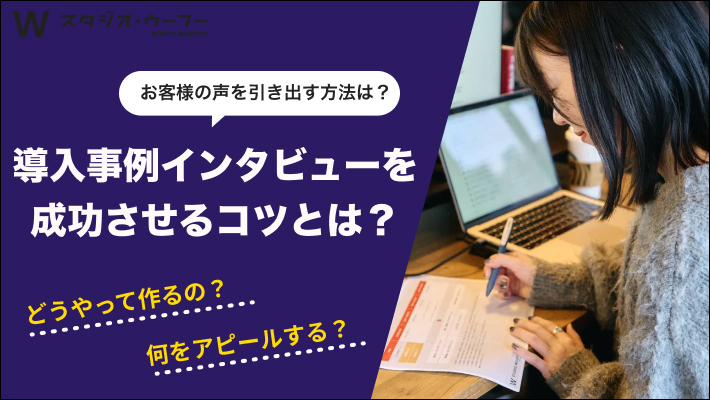効率から意味へーー「名指しされるブランド」をつくる編集設計

執筆
STUDIO WooFoo Inc.|andSTORY Inc.|Producer
K.Y.
効率の追求よりも意味の探索を
成果が伸び悩むプロジェクトでも多くの場合、工程自体はわりとスムーズに進捗する。精緻に組まれたKPIツリーは随時更新され、制作進行表も日・週単位で終了タスクが塗りつぶされる。しかし、施策を重ねるほどに数字の反応は鈍くなり、経営会議ではプロジェクト責任者が毎回肝を冷やす。
そのうち、(プロジェクト責任者の)判断の根拠は薄いまま現場による施策実行の速度だけが上がっていく。プロジェクトの方向性を検証する手順が省かれるようになり、目先の指標の達成それ自体が目的化していくのだ。結果として投下される予算と実行される施策数は増えるかもしれないが、プロジェクトの成果は顧客の記憶に残らないーー。
この文章では”効率”という言葉を、要素の分解と指標化による管理性の向上というニュアンスで使う。タスクを細分化し、各工程の所要時間とコストを可視化し、PDCAサイクルを回すことで再現性を高める手法を支える概念と言い換えてもいい。この手法、あるいは手法を支える考え方は、例えば、製造業のラインオペレーション業務では有効に機能するが、マーケティングの戦略立案やブランディング支援領域においては諸手を上げてその使い勝手の良さを称賛することは難しい。
その理由の第一として、要素間の相互依存の軽視を助長しやすい点が挙げられる。コンテンツの訴求軸と営業トークの一貫性、Webサイトの言葉選びと商談時の顧客の反応、これらは本来、独立変数としては扱えない要素なのだが、KPIツリーでは別々の担当者に割り振られることがままある。
第二に、指標そのものが目的化するリスクである。Webサイトのページビュー数やホワイトペーパーなどのダウンロード数は測定できるが、「なぜその顧客がその資料を求めたか」「他社ではなく自社を選ぶ理由として何が作用したか」は数えられない。数えられないものはいつしか忘れられていく。
第三に、プロセスの遵守が成果の代替物になるという奇妙な現象がたびたび発生する。制作工程が予定通りに進んでいることで安心し、施策が顧客の文脈で意味を持つか、という検証が後回しになる。
一次情報で仮説を磨く
“意味”とは、顧客の文脈における問題の本質と(企業や製品)ブランドの必然性を結ぶ仮説的把握のことだと考えてほしい。顧客は常に課題を抱え、何らかの解決策を探している。その探索過程で顧客はどのようにブランドを想起するだろうか、どのような言葉でブランドを語るだろうか、なぜ他社ではなくあなたが所属する企業に問い合わせるのか。
この問いの連鎖における固有の理由(答え)が企業サイドで明確でなければ、いかに美しいクリエイティブを作っても、あるいは、数値目標を精緻に設定しても、成果の達成状況は安定しない。
代表的な事例として、ある製造業向けSaaS企業のケースを匿名化して示す。この企業はリード獲得数を前年比150パーセントに設定し、Web広告とSEO記事の制作本数を倍増させた。KPIツリー上では各施策が目標を達成したが、商談化率は前年並みにとどまり、受注単価は低下した。営業担当者にヒアリングをすると、「リードの質が落ちている」「課題認識が浅い問い合わせが増えた」という声があがった。
原因は、施策が量の拡大に最適化され、「誰のどの問題を解くために存在するか」という仮説が更新されていなかったことにある。SEO記事のテーマ選定は検索ボリュームを基準とし、広告コピーは競合との差分を羅列した。結果として顧客は「何か便利そうなツール」として認知はしたが、「この課題を解決するならこの企業のこのツール」という指名には至らなかった。
KPIツリーのロジックと数値設定が正しくても成果が出ないのは、数字が語れない領域ーー想起のされ方、指名の理由、営業現場で再現される言葉ーーがマーケティング戦略の全体設計から欠落していたからである(他にも要因はありそうだが)。
対比的に示せるのが、別の産業機械メーカーの事例である。この企業は新製品のローンチにあたり、従来のカタログ制作をいったん停止し、最初の二週間を既存顧客へのインタビューに充てた。質問は「既存製品をどのような場面で使っているか」「なぜ他社製品ではなく当社を選んだか」「導入後に予想外だった使われ方はあるか」の三点に絞った。
収集された一次情報から浮かび上がったのは、カタログスペックには記載されていない「メンテナンスの容易さ」と「現場担当者が説明書なしで操作できる直感性」だった。これを仮説として、新製品の訴求軸を「高出力」から「現場が止まらない設計」に変更した。
制作物はカタログではなく、実際の工場で撮影した三分間の動画一本と、メンテナンス手順を写真で示す一枚物のチラシに絞った。すると、制作コストは当初予算の六割で済み、商談時に「あの動画の機械」と名指しされる頻度が増え、初年度の受注額は目標の120パーセントに達した。仮想事例ゆえの単純な展開だが、言いたいことはわかってもらえると思う。
ここでの成功要因は、効率を無視したことではなく、意味の確定を先に済ませたことで無駄な制作物を作らずに済んだ点にある。
意味先行の編集設計
制作会社との協業による制作実務において、あなたが発注者の立場なら、この「意味先行の編集設計」は次の順序で実装されるだろう。
まず「問い」を立てる。顧客は誰で、何に困っているか。その困りごとを(借り物ではない)自分自身の言葉で表現できているか、それとも個人的または組織的に、曖昧模糊とした断片的なイメージ群として潜在しているままか。
次に「仮説」を構築する。この問いに対して企業が提供できる固有の答えは何か。競合との違いはどこにあり、それは顧客の文脈で意味を持つか。仮説は暫定的であり、検証によって更新される前提で組み立てる。ここまでの段階ではまだ制作物のメディア形式は決めない。
次に「一次情報」を収集する。既存顧客へのインタビュー、営業担当者が記録した商談ログ、失注理由の分析、製品が実際に使われている現場の写真や動画、カスタマーサポートに寄せられた質問、そこで使われる個別具体的な言葉である。
これらは定量調査では捉えられない文脈と語彙を含んでおり、仮説の精度を磨き上げる材料となる。重要なのは、この工程を省略しないことである。一次情報なしに制作に入ると、訴求軸が制作者の主観か、競合の模倣にとどまる。収集期間は一週間から二週間が目安で、量より質を優先する。五件の深いインタビューは、百件のアンケートより鋭くて深い洞察をもたらす。
一次情報を踏まえて意味を確定する。顧客がこのブランドを想起し、指名し、語る理由として強い影響力を発揮する「核となる要素」は何か。それは一言で言えるか。営業担当者が商談で再現できる言葉になっているか。
社内で「それは違う」と反論が出る要素があれば、その反論を掘り下げて仮説を修正する。意味が定まれば、ようやくメディアの「形式」を選べる。動画か、記事か、イベントか。長さ、トーン、配信チャネルは、メディアに乗せて発信するメッセージの真意を最も効果的に伝達する手段として選択される。この順序を逆にすると、「動画を制作する」「記事を作る」ことが目的化し、何を伝えるかが後付けになる。
三つの反論
この方法論に対しては三つの反論が予想される。第一に、スピードが落ちるのではないかという懸念である。しかし実際には、意味の確定に一、二週間を投じることで、後続の制作工程で発生する「訴求軸がぶれたので作り直し」「経営陣のレビューで差し戻し」といった手戻りが減少し、ゴールへの到達時間は短縮される。
第二に、定量化が難しいという指摘である。これに対しては、短期の指標として「想起テスト」「指名検索の比率」「営業現場で顧客が使った言葉の再現記録」を設定し、中期では「案件化率の非価格弾力性」、つまり価格以外の理由で選ばれる割合や、「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)に対する物語一貫性の影響」、すなわち初回接触から受注までのメッセージの一貫性がLTVに与える相関を測定する試みが可能である。
第三に、経営会議で説明しづらいという不安である。これについては、意味の仮説を一枚のスライドで示し、その仮説を検証するために必要な一次情報の収集計画と、仮説が正しい場合に期待される指標の変化を併記することで、検証可能性を担保できる。経営陣が求めるのはプロジェクトの確実性ではなく、判断の根拠とその判断に至ったロジックの妥当性である。
明日からできる最小アクション
あなたが明日から実装できるアクションの最小単位は、発注ブリーフ(制作依頼書)の再定義だろう。外部の制作会社に対する従来のブリーフが主に「何を作るか」を指定していたのに対し、意味先行のブリーフは「誰のどんな問題を解くか」「非対象は誰か」「一次情報として何を収集したか」「暫定的な固有語(プロジェクトで使われる独自の表現。紋切り型ではない言葉の組み合わせ)は何か」を明記する。
例えば「中小製造業の経営者向け動画」ではなく、「従業員20名規模の金属加工業で、受注変動に悩む経営者が、既存設備の稼働率向上によってキャッシュフローを安定させる方法を知るための動画。非対象は大企業および設備投資余力のある企業。一次情報として既存顧客三社の現場撮影と経営者インタビューを実施済み。固有語の暫定案は『止まらない工場』」と書く。このブリーフを基に、社内レビューはメディア形式のチェックではなく、「この問いは正しいか」「一次情報から導かれる意味は妥当か」「固有語は営業現場で再現可能か」を検証する場として再設計する。
効率を否定しているわけではない。問題は順序である。メディア形式に先んじて意味を確定し、意味に従って効率を追求することで、「選ばれる」ブランドから「名指しされる」ブランドへと移行する確度が高まる。選ばれるブランドは比較検討の結果として残るが、名指しされるブランドは比較の手前で想起される。
この違いは、施策の積み重ねではなく、設計の根幹における判断の順序から生まれる。あなたが自社で試せる最初の行動は、次回の制作案件において、制作物のメディア形式を決める前に一、二週間を使って一次情報を集め、そこから導かれる意味の仮説を一行で書き出すことである。
その一行が社内で共有され、営業担当者が商談で同じ言葉を使い、顧客がその言葉を引用して自社を語るようになったとき、KPIの数字は後からついてくる。ブリーフを再定義し、KPIを意味の検証指標として再設計し、制作工程の順序を並べ替えることが、成果の伸び悩みを打開する実務上の起点となる。
image: powered by Ideogram 3.0 Turbo