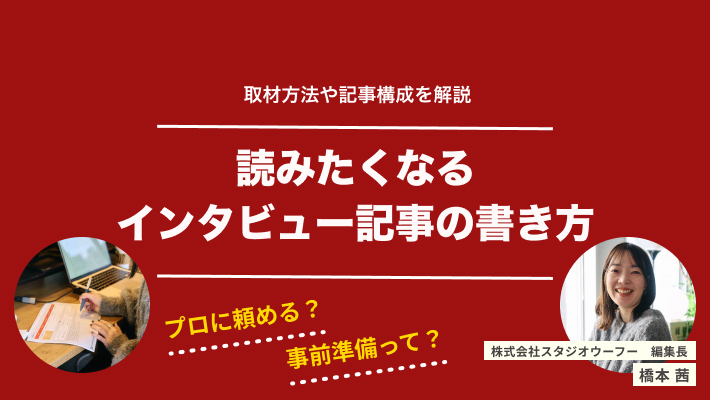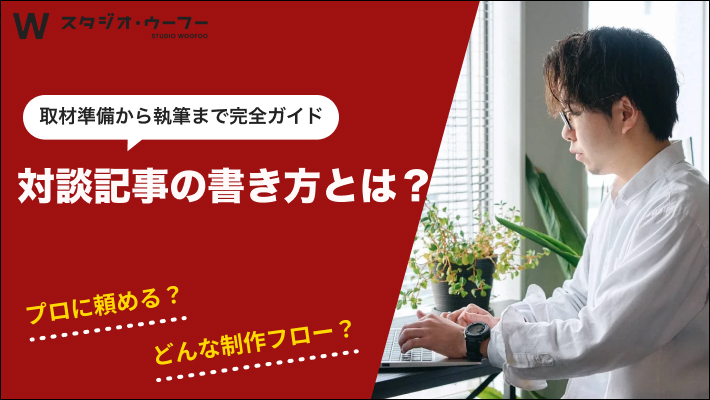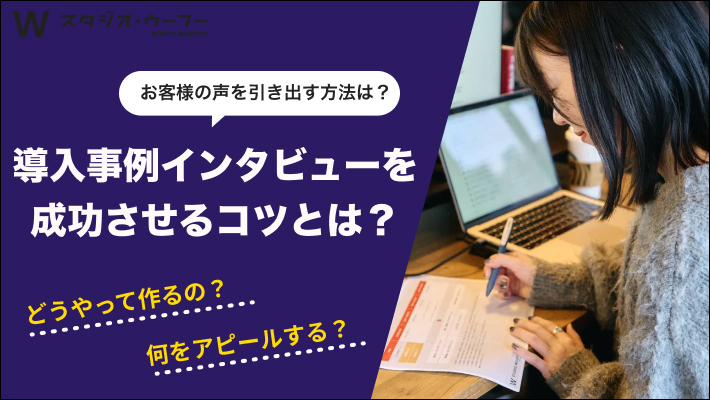
導入事例インタビューを成功させるコツとは?お客様の声を引き出す方法は?

監修
プロデューサー
谷古宇浩司
20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修
編集企画チーム/リーダー
橋本茜
1992年、大分生まれ。大学在学中に編集の仕事に憧れ、ブランディング会社で経験を積む。その後、現場のディレクションを学ぶために上京し、女性マーケティングを主軸とした編集プロダクションに勤務。アパレルを中心にカタログ制作やファッション誌の企画、撮影や誌面のディレクションを経験した。紙媒体だけでなく、Web業界での経験や知見も深めるため、2021年に株式会社アンドストーリー/株式会社スタジオ・ウーフーに入社。これまでの経験を活かし、編集ディレクターとして多種多様なコンテンツ制作に従事しつつ、チームマネジメントも手がける。
導入事例インタビューが持つ3つの効果
導入事例インタビューは単なるお客様の声にとどまらず、営業・広報・マーケティング活動を支える強力なコンテンツ資産です。ここでは、BtoB領域で導入事例インタビューがもたらす代表的な3つの効果を解説します。
BtoB導入事例インタビューが持つ3つの効果
自社サービスの認知拡大に貢献する
導入事例インタビューは、自社サービスの具体的な活用イメージを提供することで、まだ接点のない潜在層にもブランドの存在を知らしめる効果があります。特に、事例に登場する企業が読者にとって身近な業界や企業規模であれば、「自分たちも同じ課題を持っている」と自社のニーズと重ね合わせてもらえるでしょう。
また、事例コンテンツは検索にも強く、適切なキーワード設計とSEO対策を施すことで、指名検索では届かない層へのアプローチも可能になります。ホワイトペーパーや展示会での配布資料としても活用できるため、1つの事例が複数のチャネルで認知拡大を担う、非常に費用対効果の高い資産となるのです。
見込み顧客の意思決定を促進する
BtoB商材は価格や導入ハードルが高いため、検討段階で「失敗したくない」「本当に効果があるのか」と不安に感じる担当者も多いものです。そんなとき、他社の導入事例は最も信頼される意思決定材料になります。
なぜなら、実際のユーザーの声が「営業トークではない本音」として伝わり、説得力を持つからです。特に、自社と似た課題を抱えていた企業が登場し、課題→導入→効果のストーリーが明確に語られていれば、読者は自社の未来像を具体的にイメージできます。
「この企業でも成果が出たなら、自社でも導入できるかもしれない」と心理的ハードルを下げ、決裁を後押しする強力なエビデンスとなるのです。
リアリティと信頼性が増す
導入事例インタビューは、製品のスペックや機能では伝えきれない人の視点や現場の温度感を読者に届けます。インタビュー形式にすることで、導入に至った背景や実際の現場での苦労、想定外の活用効果など、パンフレットや製品ページでは表現できないリアルな情報が詰め込まれます。
さらに、顧客企業の担当者が実名・顔出しで登場することで、そのコンテンツ自体の信頼性が一気に高まります。匿名レビューとは異なり、読者にとって「信じられる情報源」となるのです。企業としての透明性も印象づけられ、ブランドイメージの向上にもつながるでしょう。

谷古宇浩司
導入事例インタビューは、自社サービスを訴求するうえで欠かせないものです。お客様が導入に至った背景や実際の効果などを見せることで、他のお客様がサービスを検討する材料となります。インタビューを打診する際には、記事冒頭でお客様のサービスについて紹介するなど、双方にメリットを提案することが重要です。
導入事例の型は2つ!目的別の使い分けが重要
導入事例インタビューには、目的や伝えたいメッセージに応じて適した「型」があります。ここでは、代表的な2種類の構成である「Before/After型」と「ストーリー型」について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。
BtoB導入事例の型は2つ!目的別の使い分けが重要
Before/After型
Before/After型は、導入前の課題→導入の背景とプロセス→導入後の成果という一連の流れで構成される、最もスタンダードで再現性の高いフォーマットです。読者は課題に共感しながら、導入に至るまでの検討プロセスを追体験できるため、サービスの必要性と効果を納得感を持って理解できます。
また、「課題は◯◯だったが、導入後は◯%改善された」といった定量的変化を盛り込むことで、より説得力が増し、意思決定の後押しにもつながります。さらに、課題や解決策が明確に整理されているため、比較検討中の複数サービスの中で、選ばれる確率が高まるのも特徴です。特に、ROIや生産性向上といったビジネスインパクトを重視する企業には有効な構成といえるでしょう。
ストーリー型(密着・ドキュメンタリー型)
ストーリー型は、インタビュー対象者の視点から出来事を時系列に追う形式で、感情や葛藤、人間関係など人間味を強調する構成です。Before/After型が論理的にサービスの価値を伝えるのに対し、ストーリー型は読者の共感を喚起し、感情面からブランドへの好意や信頼を高める効果があります。
「なぜこのサービスを導入しようと思ったのか」「現場ではどんな課題があり、どんな変化が起きたのか」など、まるでドキュメンタリーを読むような臨場感が生まれ、読後の記憶にも残りやすくなります。SNSやオウンドメディアでの拡散にも向いており、共感性の高いBtoB事例コンテンツとして近年注目を集めています。人材、教育、地域密着型サービスなど人の関わりが重視される業種では特に有効な型といえるでしょう。

谷古宇浩司
どの形式を取っても、お客様の課題を解決したことを伝えます。そして実際に、会社内部でどういった苦悩や葛藤があったのか、どのように解決を図ったのかをありありと描くことで、お客さまに「自社と同じような状況だ」と思ってもらえる“親近感のある導入事例”に仕上がります。
読者に刺さる導入事例の作り方
導入事例は、構成や聞き方次第で単なる取材記事にも強力な営業ツールにもなります。このセクションでは、読者の共感と信頼を獲得し、最終的に行動を引き出すための4つのステップを具体的に紹介します。
読者に刺さるBtoB導入事例の作り方
STEP①:課題や背景(読者の共感)
読者の興味を引くには、まず「これは自分の会社にも当てはまりそうだ」と思わせることが重要です。そのためには、インタビュー冒頭で課題の描写を丁寧に行う必要があります。「月初の棚卸作業に丸2日かかっていた」「属人化が進み、業務の引き継ぎができなかった」など、具体的な業務レベルでの課題提示が効果的です。
また、業界特有の事情や社内文化、決裁構造など、背景要素もあわせて描写することでリアリティが増し、読者の「うちもそうなんだよな…」という共感が引き出せます。質問例としては、「導入前、どんな業務上の悩みがありましたか?」「それによって社内にどんな影響が出ていましたか?」など、ストーリーの入口として自然に語ってもらえる設計が重要です。
STEP②:導入の決め手と選定理由(信頼の補強)
読者が最も注目するのが、「なぜそのサービスを選んだのか」という選定理由の部分です。ここでは、自社の営業資料では語れない第三者視点での評価を引き出すことで、読者の信頼感を得られます。
質問例として「どのような選択肢と比較しましたか?」「決め手となった要素はなんでしたか?」といったものが有効です。製品スペックだけでなく、営業担当の姿勢や導入サポートの印象など、体験ベースのエピソードが含まれると読者に伝わりやすくなります。また、導入時に社内でどのような説明や調整が必要だったかなど、BtoBならではの稟議のハードルに触れることで、読者自身の状況に照らし合わせやすくなるでしょう。ここで語られる選ばれた理由こそが、次の導入検討者にとって最も有益な情報となるのです。
STEP③:成果と効果(導入後の変化)
導入の成果を伝える際は、できる限り「数値」を使ったBefore/Afterを示すことが鍵です。「月間で80時間かかっていた作業が20時間に」「問い合わせ対応件数が30%減った」など、読者がインパクトを具体的にイメージできる表現が求められます。
また、定量的な成果だけでなく、「現場スタッフの心理的負担が軽くなった」「他部署にも好影響が波及した」など、定性的な変化も見逃せません。活用の具体的なシーンや、実際に使っている社員の声を交えることで、リアルな活用イメージを描き出せます。
質問例としては「具体的にどんな変化がありましたか?」「数字として表れた効果はありますか?」「現場の反応はどうでしたか?」などが効果的です。成果の多面性を伝えることで、導入検討中の読者の背中を押す説得力が生まれます。
STEP④:今後の展望
インタビューの締めくくりには、「今後どのようにサービスを活用していきたいか」という展望を語ってもらいましょう。読者にとって事例=過去の話で終わらせず、「このサービスはこれからも使い続けられる価値がある」と認識してもらうために重要です。
例えば、「次は営業部門にも展開して全社的に活用したい」「API連携で他ツールと統合し、さらに効率化を進めたい」など、未来の活用イメージが語られることで、サービスの成長性や柔軟性もアピールできます。
また、「同じ悩みを持つ他社へのメッセージ」を添えることで、読者への共感・希望・行動の導線が強化されます。質問としては「今後の目標は?」「他の企業に何か伝えたいことはありますか?」などが有効です。最終的に「導入して良かった」という言葉で締めくくられることで、読後感の良いインタビュー記事となるでしょう。
導入事例を成功させる制作フローとは?
導入事例インタビューは「書く前」が8割ともいわれるほど、準備とプロセス設計が重要です。ここからは、企画から公開までの5ステップと、それぞれで押さえておきたいポイントを解説します。
①対象企業を選定
まずは「誰に話を聞くか」を明確にすることがスタート地点です。導入事例の信頼性や訴求力は、対象となる顧客企業の選定によって大きく左右されます。例えば、「導入規模が大きい」「業界で影響力がある」「もしくは読者層と類似性が高い企業を選ぶ」ことで、自社サービスの価値がより強く伝わります。
また、すでに導入して一定期間が経過し、成果や変化が具体的に語れるフェーズにある顧客が最適です。協力を得る際は、広報部門との調整や、コンテンツの利用目的を丁寧に伝えてください。契約書や事前合意書を交わし、情報開示範囲や原稿確認フローを明確にしておくと、後工程がスムーズになるでしょう。
②インタビュー準備
対象企業が決まったら、次に必要なのが徹底的な事前準備です。ヒアリングの時間は限られているため、無駄なく深い情報を引き出すには、事前に資料を読み込み、仮説を立てたうえで質問設計を行うことが重要です。質問票はテーマ別に構成し、「導入前の課題」「導入の決め手」「効果」「今後の展望」などストーリーがつながるように設計します。
また、事前に質問票を相手に共有しておくと、当日の回答の質が格段に上がります。併せて、写真撮影がある場合は「どの場面を撮るか」「誰が写るか」などもすり合わせておくのがポイントです。取材許可・撮影許可・掲載許可の確認も忘れずに行いましょう。
③インタビュー当日
当日は、冒頭のアイスブレイクで緊張をほぐすことが最初のポイントです。「今日はよろしくお願いします」だけでなく、軽い雑談や相手の背景に興味を示すことで、空気がやわらぎます。インタビュー中は、事前に用意した質問を軸にしつつ、流れに応じて深掘りや寄り道を加える柔軟さも必要です。
「そのとき、社内の反応はどうでしたか?」「困った瞬間ってありましたか?」など、感情の揺らぎや印象的なシーンを引き出す問いがあると、読み応えのある事例になります。また、相手が話した内容をその場で要約して確認することで、理解のズレを防げるだけでなく、信頼感を与えることにもつながります。録音・メモ・写真の3点を並行して記録し、原稿作成の精度を高めましょう。
④コンテンツ制作
インタビュー後は、録音データの書き起こしからスタートします。ここで重要なのが「事実の整理」と「読みやすさの編集」の両立です。読者視点でストーリーを再構築し、章立てと流れを整える作業を丁寧に行いましょう。
例えば、「課題→導入→効果→今後の展望」という王道パターンに沿うことで、読者の理解を妨げません。テキストだけでなく、グラフや写真、キャプションなどを加えることで、視覚的な補足やコンテンツの臨場感が増します。
また、社内レビューや顧客側の原稿チェックが発生する場合は、スケジュールに余裕を持たせておくと安心です。原稿確認時には「ニュアンス修正OK」「事実の改変はNG」などガイドラインを共有することで、編集方針がぶれずに済みます。
⑤公開
最終稿が完成したら、公開チャネルを選定します。自社サイトの導入事例ページはもちろん、メルマガ・SNS・プレスリリース・営業資料・広告ランディングページなど、多チャネルでの活用を前提に設計しておくことが重要です。
事例記事単体で終わらせず、「〇〇社の事例はこちら」など、CTA(行動導線)をセットにすることでコンバージョンにもつながります。また、SEOを意識して記事にタイトル・ディスクリプション・タグなどのメタ情報を設定して、中長期的な流入獲得も狙いましょう。
さらに、事例があることで提案資料に説得力が加わるため、営業部門との連携も欠かせません。公開後の活用設計まで含めてはじめて、導入事例インタビューは資産として機能します。
インタビューでお客様の本音を引き出す3つの方法
BtoBの導入事例インタビューで最も難しいのが、本音を引き出すことです。表面的な回答では読者の心に響かず、単なる自画自賛の記事になってしまいかねません。ここでは、担当者のリアルな体験や感情を言葉にしてもらうための、3つの実践的なアプローチを紹介します。
インタビューでお客様の本音を引き出す3つの方法
事前準備で「心理的安全性」をつくる
インタビューの質は、取材前の段取りで8割決まるといっても過言ではありません。まず、質問内容や目的を事前に共有することで、相手が安心して答えられる状態を整えましょう。例えば「質問票を事前に送っておきますので、ご確認ください」と伝えるだけでも、相手は心構えができます。
また、「公開前に原稿をチェックいただけます」「文言調整は柔軟に対応可能です」といった配慮を示すことで、率直な意見や体験談を語りやすくなるでしょう。
前述しましたが当日は、いきなり本題に入るのではなく、少し雑談を挟んで関係性を築くことも大切です。初対面で「話さなきゃ」と緊張している状態では、本音はなかなか出てきません。取材者の姿勢ひとつで、言葉の深さは大きく変わるのです。
質問の順番を工夫する
聞きたいことをすぐに尋ねるのではなく、相手が話しやすくなる順序で質問を設計することが重要です。インタビュー序盤では、業務内容や企業概要など、答えやすい「ライトな質問」から始め、徐々に導入の背景や意思決定の裏側といった深掘り質問へと進めていきます。
また、「いつ・どこで・なぜ・どう感じたか」を問うことで、より具体的で感情のこもったエピソードを引き出せるでしょう。一問一答のような形式よりも「導入当時のことを教えてください」「迷った場面はありましたか?」といった問いを投げることで、対話のテンポが自然になり、相手の本音がにじみ出やすくなります。
具体的なシーンに誘導する
本音は、感情が大きく動いた「シーン」に宿っています。だからこそ、インタビューでは抽象的な話ではなく「その時、現場でどんなことが起きていましたか?」という具合に、情景が浮かぶレベルまで話を引き出すことが大切です。
例えば、「導入前にこれは無理だと感じた瞬間は?」「導入後、社内の雰囲気がガラッと変わったエピソードはありますか?」など、実際に相手がその場にいた記憶を辿れる質問がポイントです。
エピソードベースのやり取りにすることで、回答に感情やストーリーが加わり、読者の心に残るコンテンツになります。また、感情を想起させる質問は「当時、どう感じましたか?」「社内の反応はどうでしたか?」など、内面をゆっくり開いてもらうような丁寧さが鍵になります。
動画やSNSと組み合わせた方が効果的な理由
導入事例インタビューをコンテンツ資産として最大限に活用するには、記事単体ではなく、動画やSNSなど他の媒体と連携させることが重要です。ここでは、その理由と具体的な活用ポイントを解説します。
動画やSNSと組み合わせた方が効果的な理由
SNSでの拡散性・認知効果が高い
テキスト中心の事例記事は、SEO流入には強いものの、能動的に検索してこない潜在層には届きにくい面もあります。そこで有効なのが、X(旧Twitter)やLinkedIn、FacebookなどのSNSでの拡散です。事例記事の要点や印象的なフレーズを抜粋して投稿すれば、短時間で内容が伝わりやすくなり、関心を持った人がアクセスする導線を作れます。
また、インタビュー対象者や企業が投稿をシェアしてくれることも多く、自然な形でリーチが拡大していく副次効果も期待できるでしょう。さらに、SNS上でのコメントや反応を通じて「共感」「興味関心」などの定性的なフィードバックを得られ、次のコンテンツ企画にも活かせます。
記事公開後のプロモーションを想定した設計が、成果を左右するといっても過言ではありません。
>>株式会社andSTORYのSNS運用サービス
>>株式会社andSTORYの動画制作サービス
マルチチャネル展開によりコンテンツを資産化できる
導入事例は、ひとつ制作すれば終わりではなく、複数のチャネルで再利用することで資産価値が何倍にも高まります。例えば、インタビューの音声や映像素材を使ってショート動画を制作し、YouTubeやInstagramで発信すれば、視覚と聴覚に訴える別軸の訴求ができます。
スライド資料に落とし込んで営業提案に活用したり、ホワイトペーパーに再構成したりするのも有効です。Webサイトに掲載した記事と動画を組み合わせることで、訪問ユーザーの滞在時間も向上し、SEO効果の間接的なブーストにもつながります。
1つの導入事例を「何通りにも加工して届ける」ことで、費用対効果を最大化し、マーケティング全体の成果を押し上げられるでしょう。
導入事例×SEOで流入数を増やす方法
導入事例インタビューは、営業資料としての活用だけでなく、検索エンジン経由での集客にも貢献する重要なコンテンツです。ここでは、SEOの観点から導入事例を強化するための3つのポイントを紹介します。
導入事例×SEOで流入数を増やす方法
キーワード選定を正しく行う
検索流入を狙うには、まず読者が実際に検索しているキーワードを正確に把握することが前提です。例えば「導入事例 SaaS」「社内ポータル 導入 成功事例」など、検索意図が明確な語句を選びましょう。読者のニーズにマッチしたトピックとして評価されやすくなります。
また、「成功事例」「お客様の声」「事例インタビュー」などの関連キーワードや、業界・業種名を掛け合わせたロングテールワードも積極的に盛り込みましょう。キーワードはタイトル・見出し・本文・画像のalt属性・メタディスクリプションに適切に配置し、過剰に詰め込みすぎない自然な形で使うことがポイントです。
SEOは単なるテクニックではなく、「検索ユーザーが知りたい情報に、しっかりと答えているか」という視点で設計することが成果への近道です。
読者の関心を引くタイトルをつける
記事タイトルは検索順位とクリック率の双方に影響する最重要ポイントです。タイトルにはキーワードを含めるだけでなく「誰の・どんな課題を・どう解決したか」がひと目で伝わるように工夫しましょう。例えば「バックオフィス業務を70%効率化!SaaS導入事例インタビュー」など、数字や成果を明示することで説得力が増し、読み手の関心を引きやすくなります。
併せて、ターゲット層や業界名、企業規模、職種などを具体的に示すと、自分ごと化がしやすくなり、CTR(クリック率)の向上にもつながります。また、Googleの検索結果で省略されない文字数(およそ28〜32文字)を意識し、最も伝えたい情報を冒頭に持ってくる構成にすると効果的です。タイトル設計は、SEOとコンバージョンの両方に関わる「肝」として慎重に作り込む必要があります。
独自性を担保し競合に差をつける
多くの導入事例がネット上に公開されている今、読者は「また同じような内容か」と感じた瞬間にページを離脱してしまいます。そこで意識したいのが、コンテンツの独自性です。
例えば「取材相手の人柄や背景を掘り下げる」「自社の製品以外との組み合わせ事例を紹介する」「失敗や導入時のトラブルも語る」などを盛り込んでください。単なる成功談にとどまらない等身大のストーリーは、共感や納得を生み出せます。
また、競合との差別化には、トーンや見せ方も重要です。図解・イラスト・動画・インフォグラフィックなどのビジュアル表現を使えば、同じテーマでも印象を変えられます。「他にはない切り口」があると被リンクやSNSシェアも得やすく、SEOにも好影響を与えます。独自性のある導入事例は、読者の記憶に残り、ブランドの信頼を育む力を持っているのです。
導入事例インタビューは難易度が高い
導入事例インタビューは、マーケティング施策の中でも成果が見えやすい一方で、制作のハードルが高いコンテンツでもあります。取材対象者との関係構築、正確な理解力、表現力、さらには現場のリアルな声を引き出す取材力まで、多くのスキルが必要です。
スタジオ・ウーフーでは、専門分野ごとに経験豊富なライターが在籍しており、BtoB領域における複雑な取材にも対応可能です。さらに、日本全国にクリエイターが点在しているため、地方企業の事例取材においても、移動コストを抑えながらスムーズな対応ができます。
取材から撮影、編集、校正・校閲までを一括して依頼できる体制を整えているため、企業担当者が手間をかけずに高品質な事例コンテンツを制作できます。特に「失敗したくない」「他社と差をつけたい」と考えるマーケティング・広報担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。