お役立ち記事
2025.11.14
「安いほう」で選ばれる世界から抜け出すーー今日から始めるブランドストーリー設計:実装ガイド
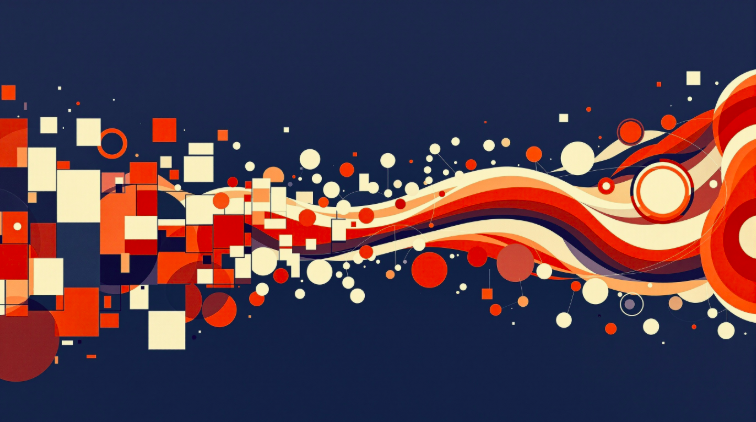
「同じサービス、同じ価格なのに競合が選ばれる」ーーこのような状況に直面したことはないだろうか。ときには、機能や価格で優位に立っているにもかかわらず、競合を選ぶ顧客が続出するケースさえある。
この問題の本質は、多くの場合、ブランドストーリーの欠如にある。明確なストーリーを持たない企業は、顧客から見れば「機能と価格を比較する表の中の一項目」に過ぎない。結果として、最終的には「より安いほう」という基準だけで判断される価格競争の世界に押し込まれてしまう。
この記事では、こうした価格競争から脱却し、顧客に「名指しで検索される」「何度も訪れてもらえる」「他者に紹介してもらえる」ブランドへと変わるための具体的な設計法を体系的に解説する。現場の一次情報をどう収集し、どう編集するか。公開後の運用方法は。そして成果をどの指標で測るのか。明日から実務で実践できる手法を具体的に示す。

執筆
andSTORY Inc.|Webユニット
花咲琢海
1. ストーリーを「作る」のをやめ、「見つける」ことから始める
強力なブランドストーリーは、美しいスローガンを「作り込む」ことでは生まれない。すでに社内に存在している事実を「見つける」ことから始まるのだ。多くの企業が最初にキャッチコピーを磨くことから始めようとするが、これは実は順序が逆なのである。
すべての土台となる「核の一文」
最初に行うべき最も重要なステップは、次の問いに答える一文を定めることである。
「誰の、どんな状況で、何がまだ解決できていないのか」
この核となる一文が曖昧なままでは、どれほど洗練されたマーケティング施策を打っても、ストーリーの芯を捉えていないため効果を発揮しない。つまり、この一文こそが、ストーリー(「戦略」と言い換えてもいいが)の骨格を支える「事実」を集めるための指針となる。
一次情報で骨格をつくる
ストーリーの骨格は、「一次情報」で構築しなければならない。一次情報とは、引用や一般論とは異なり、企業だけが持つ固有の事実である。
- 顧客から直接届いた声
- 営業担当者が記録した失注メモ
- サポート窓口に届いたメールの実際の文面
- ユーザーの実際の使用画面のスクリーンショット
- 現場での会話の記録
このアプローチを採用することで他社には決して真似のできない独自のストーリーが生まれる。なぜなら、それはあなたの会社の実際の業務から生じた本物の事実に根ざしているからである。
集めた情報を「編集」する3つの技術
集めた一次情報は、ただ並べるだけでは存在意義が希薄である。読み手との対話を生むためには「編集」する必要がある。編集とは、次の3つの技術で構成される。
- ①選択:何を削るか|すべての情報を盛り込もうとすると、かえって何も伝わらない。「全部説明したい」という誘惑を断ち切り、最も伝えたい一点に焦点を絞る勇気が重要である。
- ②順序:情報は「事実 → 解釈 → 次の一歩」の順で伝える。まず何が起きたかを示し、次にそれが何を意味するのかを伝え、最後に、ではどうするのかを示唆する。この順序が論理的な理解を促す。
- ③余白:すべてを言い切らず、あえて問いかけや選択肢を残す。この「余白」が、読み手が自分の意見で参加できる入口となり、一方的な説明を双方向の対話へと変えるのである。
ストーリー作成で守るべき注意点
編集に入る前に、陥りがちな失敗を避けるための原則を確認しておく。
- ・美談づくりに走らない:出発点は常に顧客の未解決の課題である。自社の成功物語ではなく、顧客の課題を起点にする。
- ・競合を悪者にしない:差別化のために競合を批判してはいけない。他社への尊重が自社への信頼を生む。
- ・言葉の統一を優先する:ロゴやデザインの前にまず語彙を揃える。営業、広報、採用など、どの部門が語っても一貫したブランド体験を提供できるようにする。
2. 最も価値ある情報は、生々しく、整っていない
ブランドストーリーの素材となる一次情報を集めるために、高価な市場調査は必要ない。重要なのは、日々の仕事の中に埋もれている情報を拾い上げる仕組みを作ることである。
シンプルな収集の仕組み
仕組みは驚くほどシンプルである。顧客と接点を持つ全部門(CS、営業など)を対象に、3つの項目(誰が、どの場面で、何が起きた)を記入するだけの簡単なフォームを用意し、週に3件程度の提出を依頼する。
しかし、この収集システムには、一つだけ絶対に守るべきルールがある。それは「提出する情報を整えさせない」ことである。情報を整えようとすると、現場のリアルな温度感が失われ、正確性も落ちてしまうからである。
このルールが重要な理由は3つある。
- ・提出の遅延を防ぐため:忙しい現場担当者に「きれいに書いて」と求めると、提出は後回しにされる。
- ・生の「温度感」を保存するため:顧客のフィードバックが持つ感情やニュアンスは、要約された瞬間に消え去る。
- ・正確性を維持するため:記憶を元に書き直すことで、無意識のバイアスがかかり、事実が歪むのを防ぐ。
誤字脱字があっても構わない。原文のままの、生々しく整っていない情報こそが、本物のブランドストーリーを構築するための最も価値ある原材料なのである。
運用を継続させる3つのコツ
仕組みを作っても、その仕組で運用を継続しなければ意味がない。以下の3つのコツで、情報収集を文化として社内に根付かせる。
- ・ハードルを下げる|「3行だけでOK」「写真一枚だけでもOK」と繰り返し伝え、完璧を求めない姿勢を徹底する。低いハードルが継続的な投稿を促す。
- ・称賛の文化をつくる|よい投稿があれば週に一度社内で共有して称賛する。「今週のベスト情報」として表彰するのもよい。「こういう情報が価値を持つ」という基準が共有され、投稿の質が自然に向上する。
- ・連載化する|よい投稿があれば週に一度社内で共有して称賛する。「今週のベスト情報」として表彰するのもよい。「こういう情報が価値を持つ」という基準が共有され、投稿の質が自然に向上する。
3. ストーリーは独り言ではない。「往復」である
このようにして収集した一次情報を素材にして、ブランドストーリーを制作する(この記事では、制作のプロセスは割愛する。別の記事で解説する予定)。そして、公開をするわけだがーー、多くの企業はここで過ちを犯す。「公開したら終わり」としてしまうのである。ストーリーに命が吹き込まれるのは、公開された後である。では、「後」に何があるのか。顧客との対話だ。(顧客との)対話を生むには以下の3つのステップを踏めばよい。
対話を生む「往復」のサイクル
- ・公開する:なにはともあれ、まずはストーリーを世に送り出す。
- ・分析する:集まったコメント、寄せられた質問、営業チームからのフィードバックなど、あらゆる反応を丁寧に収集・分析する。
- ・更新する:反応から得られた学びをもとに「当初の仮説」を更新し、ストーリーを編み直す。
- ・再び届ける:改良したストーリーを再び世に送り出す。
このサイクルこそが、一方的な「放送」を双方向の「対話」へと変えていく。
期待を育てる「連載」という発想
ブランドストーリーを単発ではなく「連載」として捉えることで、顧客との関係は劇的に変わる。例えば、以下のような章立てで継続的に届けてみる。とても陳腐だが、いつの世も、失敗→学び→成功の物語は人気がある。
- 第1回: なぜこの課題に取り組むのか
- 第2回: 現場で見つけた3つの兆候
- 第3回: 最初の試行錯誤と失敗
- 第4回: 転機となった顧客の一言
- 第5回: 現在の到達点と次の挑戦
もしかしたら、読者の中に「次も読みたい」という期待が生まれる(かもしれない)。読者は単なる情報の受け手ではなく、ストーリーの進展を見守る伴走者なのである。
伝える「場」に合わせて形を変える
核となるメッセージは一つでも、伝える媒体によって(メッセージの)最適な形は異なる。
- ・長文コンテンツ(ブログ記事・ホワイトペーパー): 背景や文脈を丁寧に語り、深い理解を促す。
- ・SNS(X, LinkedInなど): 「この状況、どう思いますか?」といった短い問いかけで対話のきっかけを作る。
- ・ウェビナー・セミナー: 参加者からの質問を受け付け、リアルタイムの対話を通じてストーリーを深める。
- ・営業資料・提案書:相手の課題に合わせてメッセージをカスタマイズし、解決策を端的に示す。
一貫したメッセージを、その場に最適な形で表現することで、どの接点でもブランド体験が統一される。
4. PVを測るな。サインを測れ
ブランドストーリーの成功をページビュー(PV)のような瞬間的な指標で測るべきではない。「選ばれる」という現象は、時間をかけて関係性が深まることで生まれる。したがって、指標もその関係性の深まりを反映するものでなければならない。真に「選ばれるブランド」になっているかを見極めるには、次のサインを確認する。
サイン1:名前で呼ばれているか
顧客がブランドを認知し、わざわざ探してくれているかもしれない。
確認すべきこと
- 検索エンジンでの「指名検索」の比率は増えているか?
- 「〇〇社に相談したい」という名指しでの問い合わせは来ているか?
- 営業担当者は「御社のことを調べて、ぜひ聞きたいと思った」と言われているか?
サイン2:続きが待たれているか
もしそうであると感じるなら、顧客はあなた(あなたが属している企業)の活動に関心を持ち、関係を継続したいと思っているのかもしれない。
確認すべきこと
- Webサイトへの「再訪率」やコンテンツの「保存率」は高いか?
- メールマガジンの開封率や、連載コンテンツの読了率は伸びているか?
サイン3:(顧客に)守られているか
顧客との間に深い信頼関係が築かれている可能性が高い。
確認すべきこと
- 製品トラブルや批判が起きた時、顧客や支持者から自然な擁護や好意的なコメントが寄せられるか?
- 「いつもお世話になっているので改善を待っています」といった声が上がるか?
サイン4:顧客と一緒につくっている感覚があるか
そう感じるのであれば、顧客は単なる「買い手」から、ブランドを育てる「パートナー」へ変わりつつあるのかもしれない。
確認すべきこと
- ユーザーによる事例投稿(UGC)やSNSでの言及は増えているか?
- 新製品の共同開発や改善企画への参加者はいるか?
見落とされがちな重要指標
上記に加えて、組織の健全性を示す以下の指標も重要である。
- 社内の学習指標: FAQや失注理由の「更新回数」をチェックする。頻繁な更新は、組織が顧客の声から学び、改善を続けている証拠である。
- 採用における応募の質: 「御社の〇〇という取り組みに共感し、自分の△△の経験を活かしたい」といった、具体的で熱意ある応募者が増えているかを確認する。
これらすべてのサインが揃った時、ブランドは価格競争を超えて、真に「選ばれる存在」になる。
5. 完璧なストーリーを待つな。明日、「第0回」を公開せよ
最後に。
多くの企業が罠にはまる。「『完璧なブランドストーリー』を完成させてから公開しよう」という危険なトラップに。
しかし、それでは公開が遅れるだけでなく、市場から貴重なフィードバックを得られる機会を失ってしまう。では、どうすればいいか。最も効果的なアクションは、「第0回」を公開することである。これは完成された物語ではなく、これから何を語ろうとしているのかというあなたの会社の「意思表示」でもある。
「第0回」で伝えるべき3つのこと
- ①なぜこのテーマに取り組むのか(問題意識)
- ②何を目指しているのか(ゴール)
- ③どのように進めていくのか(予定)
目的は、完璧なものを作ることではなく、今すぐ対話を始めることである。
「第0回」も場に合わせて語り方を変える
- ・長文コンテンツ(ブログ記事など):これまでの経緯や問題意識の背景を丁寧に説明する。
- ・SNS(X, LinkedInなど): 「あなたの会社でも、こんな課題はありませんか?」と短い問いを投げかけ、対話のきっかけを作る。
- ・ウェビナー:「今日は、このテーマについて皆さんと一緒に考えたい」と、参加者を巻き込む。
- ・営業資料: 「現在、当社では〇〇という取り組みを進めている」と、背景情報として端的に紹介する。
このアプローチこそが、一方的な「告知」を双方向の「関係」へ変える。小さく始めて、反応を見ながら育てていくーー。この姿勢が、選ばれるブランドをつくる運用の本質である。
以上、この記事で紹介した原則は、あなたの会社のマーケティング手法の転換を促すものである。それは、美しい言葉を「作る」ことから、社内外に埋もれている事実を「見つけ、編集する」ことを意味する。そして、完成された情報を「発信する」ことから、未完成な物語で「対話し、育てる」ことへの転換でもある。さらには、完璧さを目指すことから、継続的な改善を繰り返すことへの大胆なシフト、といってもよいだろう。
さあ、明日から、あなたは何を「見つけ」、誰と「対話」を始めますか?
image: powered by flux-pro/ultra

